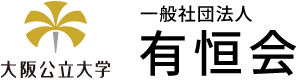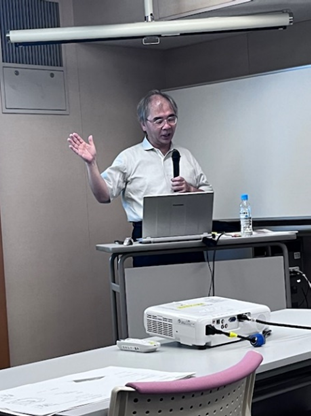第572回 有恒会 大阪北支部 例会報告
2025年7月10日、第572回有恒会大阪北支部例会が、25名(内女子大卒3名)の参加を得て、大阪駅前第2ビルの文化交流センター大セミナー室で開催されました。
今回は、大阪公立大学大学院文学研究科の仁木宏教授に、「豊臣秀吉の大坂城はどこまでわかっているか」と題してご講演いただきました。仁木教授は日本中世史、特に室町時代から織田信長、豊臣秀吉の時代の研究がご専門です。
豊臣大坂城の石垣は、1959年の大坂城総合学術調査で初めて地下から発見され、その後、豊臣時代の「詰ノ丸」の石垣であることが確認されました。秀吉が築いた豪壮華麗な大坂城は、徳川幕府によって豊臣家の権威を消し去るかのように大量の盛り土で地中に埋められ、その上に現在の大阪城が築城されたことが判明した訳です。
秀吉の大坂城は一般にはその姿はあまり知られていません。仁木教授は、大阪城本丸地区が国の特別史跡に指定されているため、発掘調査が難しい中、絵図や過去の研究を基に、4年にわたって約300地点の地下を調査し、城内各地で地下1~10数m付近に石垣や豊臣時代の地表面を発見されました。これまで絵図でしか確認されていなかった築城当時の大坂城の姿を初めて大規模に確認されたとのことです。
仁木教授には、そうした調査結果も踏まえて、豊臣大坂城の絵図をもとに、バーチャルツアー的に本丸を中心とする城の構造を詳細にご説明いただきました。
二の丸、三の丸地区の解明はまだまだのようですが、機会あるごとに豊臣大坂城の復元が進んでいくことが期待されます。
なお、発見された詰ノ丸石垣は、天守閣近くに本年4月1日にオープンした「豊臣石垣館」で見ることができると紹介されました。
大変興味深いご講演をお聞きした後は、昼食懇談会に移り、参加者相互が懇親を深め、次回を期して閉会となりました。
文責:副支部長 亀井信吾(1977年商学部卒)
| 前の記事へ | トピックス一覧 | 次の記事へ |